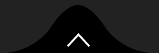明渡し・立ち退き
 明渡し・立ち退き
明渡し・立ち退き
土地建物の賃貸借契約の終了事由としては、
- 賃貸借契約の合意解約
- 賃貸借契約の解除
- 賃貸借契約の更新拒絶
- 賃貸借契約の解約申入れ
という4つの場合があります。
1.の相手方の了解の下契約を終了する合意解約のケースを除き、賃貸人の側から土地建物の明渡しを請求する際には、まず当該土地建物にまつわる契約が借地借家法の適用を受けるものであるか否かを検討することが重要です。借地借家法は借主の権利保護を目的として制定された法律であり、明渡しを請求するに際し貸主側に一定の要件を加重して要求するなど、一般に貸主側に不利に働くものだからです。
借地借家法の適用がある場合には、借主側に賃料の不払いや貸主の許可を得ていない増改築、第三者への無断転貸など、当初の賃貸借契約で定められた解除事由があるか否かを検討することも必要です。借主の側に明確な解除事由がある場合は、土地明渡し、建物明渡しに際して基本的に明渡し料が不要になり、そのうえ土地明渡し、建物明渡しを法的手段に則り迅速に行える可能性が高いからです。
他方、借地借家法の適用があり、かつ借主の側において特段の解除事由もない場合には、期間満了による更新拒絶又は解約申入れをするには、貸主の側において更新を拒絶するないし解約を申し入れるに足りる一定の「正当事由」が必要となります。
正当事由の有無に関しては、貸主から借主に対し立ち退き料の交付がなされたか否かも判断要素になります。正当事由については、資料を収集分析した上で正当事由要素を調査し、過去の判例に照らし貸主側に正当事由があることを裁判所に認めてもらえるかについて十分に吟味した上、明渡しの交渉及び裁判に臨む必要があります。
以下では、最も典型的な事例でありまた相談件数も多い、賃借人の賃料不払いを理由に建物賃貸借契約を解除するケースを例として、建物の明渡しに至る具体的な手順について御説明します。
(1)物件の現況調査
弁護士が一緒に現地に赴き、物件の現況を調査します。現在の居住状況、契約当事者と異なる第三者が建物を占有していないかなど、物件の現況を調査することにより、その後に予定している手続がスムーズに進むか否かの判断が可能になります。
(2)内容証明による催告・交渉
調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞いた上話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。まずは弁護士名で内容証明郵便を送付することによって、未払賃料の催告と賃貸借関係の解消を求める意思表示を証拠に残した上で、話し合い・交渉を開始します。
なお、このとき賃借人の了承なく合い鍵等を用いて物件内に侵入したり、また賃借人の所有物を勝手に処分したりするのは後にトラブルの元になる可能性がありますので、行ってはいけません。この時点で話し合いがまとまらない場合には、法的手段を行使することになります。
(3)占有移転禁止の仮処分
賃借人が多重債務などに陥りいつのまにか行方不明になり、物件内に得体の知れない占有者がいるというケースもあります。悪質な賃借人の場合は、物件の明渡し請求を妨害するために、わざと第三者を建物に住まわせてしまうこともあります。このような場合、賃借人を被告として建物の明渡しを認める判決を得ても、当該第三者には判決の効力が及ばず、強制執行ができないことになってしまいます。
占有移転禁止の仮処分は、建物の占有者を賃借人または仮処分時点において建物を占有している者に固定することにより、このような妨害手段を防ぐための保全手続です。
(4)賃料請求・建物明渡請求訴訟
賃借人が話し合いや交渉に応じない場合、あるいはそもそも賃借人が行方不明などの場合には、裁判所に訴訟を提起します。訴訟提起にあたっては原則として相手方の居所が判明していることが必要ですが、賃借人が失踪してしまっているようなケースでは、公示送達という特殊な手続を用いて訴訟手続を進行することになります。
(5)強制執行
裁判所からこちらの主張を認める判決を受けても、賃借人や占有者が任意に建物を明け渡さない、または賃借人が行方不明の場合などで任意の明渡しが困難な場合には、強制執行手続によって明渡しを行います。このとき賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することが出来ます。強制執行が完了すれば、建物明渡しの手続はすべて終了です。
土地建物の明渡しについては、法律に照らし当方の主張に理がある場合には基本的に手続を進行するだけですので、比較的スムーズに明渡しまで至るケースが多いです。他方で相手方の主張に理がある場合や、いずれとも判断しがたい場合には条件を譲歩して早期に解決を図るのか、或いはあくまで法的手段による決着を目指すのか微妙な判断を求められることになります。判断を誤らないためのみならず、その後の法的手続をスムーズに進めるためにも、初期の段階から弁護士に相談されることをお勧め致します。

 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス 特長
特長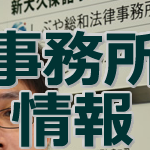 事務所情報
事務所情報 取扱業務
取扱業務 契約書
契約書 利用規約
利用規約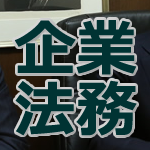 企業法務
企業法務 債権回収
債権回収 労働問題
労働問題 廃業・倒産
廃業・倒産 不動産
不動産 遺言相続
遺言相続 個人案件
個人案件 採用
採用 ニュースレター
ニュースレター Information
Information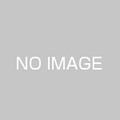 サイトマップ
サイトマップ